
ふるえ
@furu_furu
本について日記に書いていたり、書いていなかったこと。
- 2025年8月2日
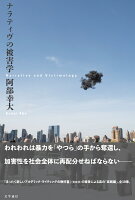 ナラティヴの被害学阿部幸大気になる
ナラティヴの被害学阿部幸大気になる - 2025年8月2日
 可能性の育み 芸術士特定非営利活動法人アーキペラゴ気になる
可能性の育み 芸術士特定非営利活動法人アーキペラゴ気になる - 2025年8月2日
- 2025年7月27日
 企業変革のジレンマ宇田川元一読んでる組織の課題を目に見える部分だけで判断しないという課題設定の部分や、何か外に答えがあるのではないかという根拠のない希望みたいなものは組織課題を抱える中でとても気をつけたい部分。
企業変革のジレンマ宇田川元一読んでる組織の課題を目に見える部分だけで判断しないという課題設定の部分や、何か外に答えがあるのではないかという根拠のない希望みたいなものは組織課題を抱える中でとても気をつけたい部分。 - 2025年7月27日
 ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡のすべてマギー・アデリン=ポコック,定木大介,平松正顕借りてきた読んでる宇宙が発見されて何もわかっていなければガンダムとか、インターステラーみたいな作品も生まれていないんだよなと思うと、感動する。今は手が届かない、目に見えるものだけだったとしても、それが一つずつ明らかにされていく中で、科学技術や創作だけではなく、未来では色んな可能性が生まれていく。そんなロマンがある。
ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡のすべてマギー・アデリン=ポコック,定木大介,平松正顕借りてきた読んでる宇宙が発見されて何もわかっていなければガンダムとか、インターステラーみたいな作品も生まれていないんだよなと思うと、感動する。今は手が届かない、目に見えるものだけだったとしても、それが一つずつ明らかにされていく中で、科学技術や創作だけではなく、未来では色んな可能性が生まれていく。そんなロマンがある。 - 2025年7月26日
 ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡のすべてマギー・アデリン=ポコック,定木大介,平松正顕借りてきた読んでる史上最大の宇宙望遠鏡。地球にはなく、宇宙に打ち上げられた望遠鏡から送られてくる写真は本当にこの世界にあるのか疑わしくなるほど綺麗な星とガスと、宇宙の黒い空間。自分たちには到底手が届かないところにあったはずなのに、人間が作り出した目ではすでに捉えられるところに来ていて、人の知的好奇心と欲望は凄まじくて好き。
ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡のすべてマギー・アデリン=ポコック,定木大介,平松正顕借りてきた読んでる史上最大の宇宙望遠鏡。地球にはなく、宇宙に打ち上げられた望遠鏡から送られてくる写真は本当にこの世界にあるのか疑わしくなるほど綺麗な星とガスと、宇宙の黒い空間。自分たちには到底手が届かないところにあったはずなのに、人間が作り出した目ではすでに捉えられるところに来ていて、人の知的好奇心と欲望は凄まじくて好き。 - 2025年7月26日
 泳ぐように光るひらいめぐみ読み終わった読んでいてホッとする日記だった。他者の日記を読んでいると、そこに書かれている料理や作品にすごく興味が出てくるけど、それはその人の感覚が自分に近かったり、好ましかったりするからなのかもしれない。食べたい料理や、見てみたいと作品も増えた。
泳ぐように光るひらいめぐみ読み終わった読んでいてホッとする日記だった。他者の日記を読んでいると、そこに書かれている料理や作品にすごく興味が出てくるけど、それはその人の感覚が自分に近かったり、好ましかったりするからなのかもしれない。食べたい料理や、見てみたいと作品も増えた。 - 2025年7月25日
- 2025年7月23日
 ルール?本水野祐,田中みゆき,菅俊一読み終わったルールを守る(使う)ことに対する主体性という話が最後の対談の部分で触れられていて面白かった。明文化することで失われる余白と、増えていくコスト。ルールをつくることはそれを守ってもらうための認識を生み出すこと、それを監視する人(対応する人かシステム)を設定しないといけなかったり、必要なコストがある。管理するということは、ルールが十全に機能している間は効率がいいのかもしれないが、そこを目指すためにはかなりのコストをかける必要があるのかもしれない。
ルール?本水野祐,田中みゆき,菅俊一読み終わったルールを守る(使う)ことに対する主体性という話が最後の対談の部分で触れられていて面白かった。明文化することで失われる余白と、増えていくコスト。ルールをつくることはそれを守ってもらうための認識を生み出すこと、それを監視する人(対応する人かシステム)を設定しないといけなかったり、必要なコストがある。管理するということは、ルールが十全に機能している間は効率がいいのかもしれないが、そこを目指すためにはかなりのコストをかける必要があるのかもしれない。 - 2025年7月22日
 泳ぐように光るひらいめぐみ読んでる言葉としては苦しいようなことが書かれていても、それを感じさせないような明るさなのか、リズムの良さなのか、すーっと読める。面白いなあと思って、すごくすごく救われている。
泳ぐように光るひらいめぐみ読んでる言葉としては苦しいようなことが書かれていても、それを感じさせないような明るさなのか、リズムの良さなのか、すーっと読める。面白いなあと思って、すごくすごく救われている。 - 2025年7月21日
 ルール?本水野祐,田中みゆき,菅俊一読んでる育ってきた中で思考に染み付いているルールが衝突というか、照らし合わされるという意味では家庭の中でのルールが1番創造的でありたいなと思う。 「ルール?展」が開催されていた時の葛藤や対応、そこで信じたかったことなどが丁寧に書かれていてとてもよかった。
ルール?本水野祐,田中みゆき,菅俊一読んでる育ってきた中で思考に染み付いているルールが衝突というか、照らし合わされるという意味では家庭の中でのルールが1番創造的でありたいなと思う。 「ルール?展」が開催されていた時の葛藤や対応、そこで信じたかったことなどが丁寧に書かれていてとてもよかった。 - 2025年7月21日
- 2025年7月20日
 ルール?本水野祐,田中みゆき,菅俊一読んでる法律とかルールにはわざと解釈を緩めているというか、余白を生み出しているような書き方で定められているものがある。時代や社会情勢によってアップデートされていく社会の形や、価値観に対応するためのものなのだろうけれど、それを運用する側にとっては扱い方が難しい。ルールを運用する人たちと、ルールが適用される(使う)人たちとの関係性が一方的なものではなく、対話の中で適応していくことができれば理想なのかもしれないが、それも他の人たちとの公平性という理由でなかなか前に進まなかったりする。どうすればルールは変化し、適応していけるのか。
ルール?本水野祐,田中みゆき,菅俊一読んでる法律とかルールにはわざと解釈を緩めているというか、余白を生み出しているような書き方で定められているものがある。時代や社会情勢によってアップデートされていく社会の形や、価値観に対応するためのものなのだろうけれど、それを運用する側にとっては扱い方が難しい。ルールを運用する人たちと、ルールが適用される(使う)人たちとの関係性が一方的なものではなく、対話の中で適応していくことができれば理想なのかもしれないが、それも他の人たちとの公平性という理由でなかなか前に進まなかったりする。どうすればルールは変化し、適応していけるのか。 - 2025年7月19日
- 2025年7月19日
- 2025年7月18日
- 2025年7月13日
 ルール?本水野祐,田中みゆき,菅俊一読んでる電車で読み進める。ルールが創造性を生み出す、とはどこか矛盾しているような感覚になるけれど、制約があることで線引きされ、内と外を認識することから新しいものが生み出されていくのかも知れない。 「ルールをつくることは、物事の枠や外縁を生み出したり、線を引く行為でもあります。一方で、ルールがその枠や線を可視化することで、逆に枠や線をはみ出すことができます。ルールがあったり、明確化されていることにより、どこから先に行けば新しいのかがわかるようになり、新しさが可視化される面があるのです。そして、線や枠をつくると、そこから一歩はみ出たくなる人が出てくるものです。(中略)これは人間に備わった好奇心やフロンティア精神によるものなのかはわかりませんが、ルールにはこのような制約や設定された線や枠を一歩越えようという人間の創造性や新たな問いを生み出す面があると言えます。」菅俊一/田中みゆき/水野祐『ルール?本』(フィルムアート社)p.80
ルール?本水野祐,田中みゆき,菅俊一読んでる電車で読み進める。ルールが創造性を生み出す、とはどこか矛盾しているような感覚になるけれど、制約があることで線引きされ、内と外を認識することから新しいものが生み出されていくのかも知れない。 「ルールをつくることは、物事の枠や外縁を生み出したり、線を引く行為でもあります。一方で、ルールがその枠や線を可視化することで、逆に枠や線をはみ出すことができます。ルールがあったり、明確化されていることにより、どこから先に行けば新しいのかがわかるようになり、新しさが可視化される面があるのです。そして、線や枠をつくると、そこから一歩はみ出たくなる人が出てくるものです。(中略)これは人間に備わった好奇心やフロンティア精神によるものなのかはわかりませんが、ルールにはこのような制約や設定された線や枠を一歩越えようという人間の創造性や新たな問いを生み出す面があると言えます。」菅俊一/田中みゆき/水野祐『ルール?本』(フィルムアート社)p.80 - 2025年7月12日
 ルール?本水野祐,田中みゆき,菅俊一借りてきた読んでる当たり前に思っていた標識も、法律とかのルールに基づいているし、看板もタダというわけではないから広告とかで費用を捻出とかあるんだろうなと読みながら、今まで知らなかったルールを見せるための背景が見えてきてたのしい。
ルール?本水野祐,田中みゆき,菅俊一借りてきた読んでる当たり前に思っていた標識も、法律とかのルールに基づいているし、看板もタダというわけではないから広告とかで費用を捻出とかあるんだろうなと読みながら、今まで知らなかったルールを見せるための背景が見えてきてたのしい。 - 2025年7月11日
 スロー・ルッキングシャリー・ティシュマン,北垣憲仁,新藤浩伸読み終わった「ゆっくり見る」ことを通して、そこにあるものを単純化させない、複雑さに面白さを見出す。それは観察にもつながり、研究へと深みを増していく行為だけれど、別にそこまでじゃなくてもいいから、見るという行為に時間をかける楽しみというものが見つかればいいなと思う。学習効果の視点からの話にもなり、複雑性を見出すことは、関係しあっているものそれぞれに見分けることにつながり、その仕組みを理解して、組み立てることを可能にしていくというような記述があって、世界に新しいものを生み出していく一歩はよく見ることなのかもしれないと思った。
スロー・ルッキングシャリー・ティシュマン,北垣憲仁,新藤浩伸読み終わった「ゆっくり見る」ことを通して、そこにあるものを単純化させない、複雑さに面白さを見出す。それは観察にもつながり、研究へと深みを増していく行為だけれど、別にそこまでじゃなくてもいいから、見るという行為に時間をかける楽しみというものが見つかればいいなと思う。学習効果の視点からの話にもなり、複雑性を見出すことは、関係しあっているものそれぞれに見分けることにつながり、その仕組みを理解して、組み立てることを可能にしていくというような記述があって、世界に新しいものを生み出していく一歩はよく見ることなのかもしれないと思った。 - 2025年7月11日
 古くてあたらしい仕事島田潤一郎かつて読んだ本棚を整理していてふと目についたので改めて少し読んだ。読書をすることの面白さを確かなものにしてくれる文章に、救われている気がする。 「現実の世界だけでは、ときどき、たまならく苦しい。逃げる場所もないようにみえる。それは、スマートフォンでニュースを見ていても、SNSを見続けていても同じだ。けれど、現実に流れる時間とは別の、もうひとつの肥沃な時間を心のなかにもつことができれば、日々はにわかにその色を取り戻す。本を読むことは、音楽に耳を澄ませることは、テレビの前でスポーツに熱中することは、現実逃避なのではない。その世界をとおして、違う角度から、もう一度現実を見つめ直すのだ。あるいは、そうした虚構のフィルターをとおして、悲しみやつらいことを時間をかけて自分なりに理解するのだ。必要なのは知性ではなく、ノウハウでもなく、長い時間だ。現実に流れる時間とは異なる時間を、自分以外のどこかに求めること。そうすることで、生きることはだいぶ楽になる。素晴らしい作品は、いつまでも心のなかから消えず、それは内側から生活するものを支える。」島田潤一郎『古くてあたらしい仕事』(新潮社)p.192,193
古くてあたらしい仕事島田潤一郎かつて読んだ本棚を整理していてふと目についたので改めて少し読んだ。読書をすることの面白さを確かなものにしてくれる文章に、救われている気がする。 「現実の世界だけでは、ときどき、たまならく苦しい。逃げる場所もないようにみえる。それは、スマートフォンでニュースを見ていても、SNSを見続けていても同じだ。けれど、現実に流れる時間とは別の、もうひとつの肥沃な時間を心のなかにもつことができれば、日々はにわかにその色を取り戻す。本を読むことは、音楽に耳を澄ませることは、テレビの前でスポーツに熱中することは、現実逃避なのではない。その世界をとおして、違う角度から、もう一度現実を見つめ直すのだ。あるいは、そうした虚構のフィルターをとおして、悲しみやつらいことを時間をかけて自分なりに理解するのだ。必要なのは知性ではなく、ノウハウでもなく、長い時間だ。現実に流れる時間とは異なる時間を、自分以外のどこかに求めること。そうすることで、生きることはだいぶ楽になる。素晴らしい作品は、いつまでも心のなかから消えず、それは内側から生活するものを支える。」島田潤一郎『古くてあたらしい仕事』(新潮社)p.192,193
読み込み中...


